税理士として独立開業を考えている方の中には、「バーチャルオフィスを使って開業できないだろうか」と考える方も多いのではないでしょうか。
働き方の多様化やコスト削減の観点から、バーチャルオフィスへの注目が高まっています。
残念ながら税理士業務においては、バーチャルオフィスのみでの開業は認められていません。
税理士法や関連法規により、実際に業務を行うための物理的な事務所の設置が義務付けられているためです。
本記事では、税理士がバーチャルオフィスで開業できない理由を詳しく解説し、バーチャルオフィスの適切な活用方法、さらには開業時に利用できる代替案についてご紹介します。
これから開業を目指す税理士の皆様にとって、実用的な情報をお届けします。
税理士がバーチャルオフィスで開業できない理由5選

税理士がバーチャルオフィスで開業できない理由は、税理士法をはじめとする関連法規に明確に定められています。ここでは、その主な理由を5つの観点から詳しく解説します。
- 物理的な作業スペース・業務設備があること
- 実態として継続使用できる場所
- 人的・物的設備の必要性
- 事務所所在地が「自らの管理下」にあること
- 登録・許認可実務においては不可
それぞれ詳しく解説します。
物理的な作業スペース・業務設備があること
税理士業務を行うためには、実際に業務を遂行できる物理的な作業スペースと必要な設備を整えることが法的に義務付けられています。
税理士法第40条では、税理士は事務所を設けなければならないと明記されており、この「事務所」とは単なる住所貸しではなく、実際に業務を行う場所を指します。
具体的には、帳簿類の保管場所、パソコンやプリンターなどの事務機器、顧客との打ち合わせスペース、書類作成のためのデスクなどが必要です。
物理的設備がなければ、適切な税理士業務を提供することは困難であり、品質の担保も難しくなるでしょう。
バーチャルオフィスは住所貸しや郵便物の受け取りサービスが中心であり、実際の業務を行うための設備や環境を提供するものではありません。
実態として継続使用できる場所
税理士事務所として登録する場所は、実態として継続的に使用できる場所でなければなりません。事務所は「継続して使用する場所」と定義されており、一時的な利用や不定期な使用は認められていません。
上記は、税理士が顧客に対して安定したサービスを提供し、責任を持って業務を遂行するための重要な要件です。
バーチャルオフィスは本来住所貸しサービスであり、実際にその場所で継続的に業務を行うことを前提としていません。また、バーチャルオフィスでは顧客が緊急時に直接訪問した際、税理士本人が不在であることが頻繁に発生する可能性があります。
税理士は顧客の重要な財務情報を扱うため、いつでも責任を持って対応できる体制を整えておく必要があり、バーチャルオフィスではこの要件を満たせません。
人的・物的設備の必要性
税理士業務を適切に遂行するためには、人的・物的設備の両面で十分な体制を整える必要があります。人的設備については、税理士本人はもちろん、必要に応じて補助者やスタッフが常駐できる環境が求められているわけです。
物的設備については、会計ソフトや税務ソフトが稼働するパソコン、大量の書類を保管できるキャビネット、プリンターや複合機、顧客との面談に必要な会議室や応接スペースなどが含まれます。これらの設備は、単に所有するだけではなく、実際の業務で継続的に使用できる状態で維持管理する必要があります。
バーチャルオフィスでは、このような包括的な設備を提供することはできず、税理士業務に必要な環境を整えることは不可能です。
事務所所在地が「自らの管理下」にあること
税理士事務所の所在地は、税理士自身が管理・運営できる場所でなければなりません。業務の品質管理、機密情報の保護、顧客対応の責任体制を確保するための重要な要件です。
税理士法では、税理士が事務所の運営について全責任を負うことが定められており、第三者が管理する場所では、この責任を適切に果たせません。
バーチャルオフィスは運営会社が管理する共有スペースであり、税理士が独立して管理することは不可能です。
また、郵便物の受け取りや来客対応も運営会社のスタッフが行うため、税理士業務に関する重要な情報が第三者を経由することになり、税理士の守秘義務や独立性を維持できません。
さらに、緊急時の対応や、税務署などの行政機関からの調査があった場合の対応も、税理士が直接管理できない環境では適切に行うことが困難です。
登録・許認可実務においては不可
税理士として開業するためには、日本税理士会連合会および所属する税理士会への登録が必要です。登録手続きにおいてバーチャルオフィスの使用は認められていません。
税理士法第18条に基づく開業届出書の提出時には、事務所の所在地として実際に業務を行う場所を記載する必要があり、単なる住所貸しサービスでは受理されないのです。
税理士会による事務所調査では、実際に業務を行うための設備や環境が整っているかどうかが確認されます。調査において、バーチャルオフィスのような住所貸しサービスでは、必要な要件を満たしていないとして登録が認められない可能性が高いでしょう。
また、税理士業務に関する各種許認可や届出においても、実態のある事務所の存在が前提となっています。
たとえば、電子申告の利用届出や、特定の業務に関する承認申請などでも、事務所の実在性が重視されます。このように、制度上の要件からも、バーチャルオフィスでの開業は不可能なのです。
税理士がバーチャルオフィスを使うメリット

税理士は一部の業務でバーチャルオフィスを使用することが可能です。バーチャルオフィスを使うメリットを解説します。
- コストを削減できる
- 都心部の住所を使える
- プライバシーやセキュリティが守れる
- 来客対応に使える
詳しく見ていきましょう。
コストを削減できる
バーチャルオフィスの最大のメリットは、大幅なコスト削減効果です。都心部に実際のオフィスを借りる場合、賃料だけでも月額数十万円から数百万円の費用が発生しますが、バーチャルオフィスなら月額数千円から数万円程度で利用できます。
初期費用も、敷金・礼金・仲介手数料などが不要なため、開業時の資金負担を大幅に軽減できるでしょう。また、光熱費や通信費、清掃費などの維持費も削減でき、固定費の圧縮により経営の安定性が向上します。
開業初期の税理士にとって、限られた資金を有効活用できる点は大きなメリットです。
浮いた資金を税務ソフトの導入や研修費用、マーケティング活動に充てると、より質の高いサービス提供や事業拡大に集中できるでしょう。さらに、契約期間の柔軟性により、事業規模の変化に応じて迅速に対応できる点も、経営リスクの軽減につながります。
都心部の住所を使える
バーチャルオフィスを利用すると、登録上の事務所が郊外や地方にあっても、都心部の一等地住所を営業活動に活用できるため、顧客に対する信頼性の向上や、ブランドイメージの向上につながるでしょう。
登録事務所が郊外にある場合、顧客が来訪することが難しくなるでしょう。そういったケースでアクセスのよい都心部の会議室を利用すると、利便性が保たれます。
また、同業他社との差別化を図る上でも効果的です。交通アクセスの良い立地の住所を使用すると、顧客にとっての利便性をアピールできるでしょう。
さらに、複数の都心部住所を使い分ければ、異なる地域の顧客に対してより身近な存在として認識してもらえる可能性があります。
ただし、実際の業務場所と異なる住所を使用する場合は、顧客に対して適切な説明を行い、誤解を招かないよう注意が必要です。
プライバシーやセキュリティが守れる
自宅を主たる事務所として使用している税理士にとって、バーチャルオフィスはプライバシー保護に役立ちます。
自宅住所を営業活動に使用することで生じるセキュリティリスクを回避できるでしょう。特に、インターネット上での住所公開や、不特定多数の人に住所を知られることによるリスクを軽減できます。
家族のプライバシーも保護され、仕事と私生活の境界を明確にできるでしょう。さらに、営業時間外の来客や電話対応についても、バーチャルオフィスの転送サービスを活用すると、適切な対応が可能になります。
バーチャルオフィスの電話転送サービスであれば24時間対応の体制を自力で整えることなく、顧客サービスの向上を図れます。データセキュリティの観点からも、重要な書類の保管場所を分散できる点もメリットです。
来客対応に使える
バーチャルオフィスの会議室やラウンジスペースは、来客対応において有効な設備です。自宅事務所では対応が困難な大人数の会議や、重要な商談の場として活用できます。
プロフェッショナルな環境での顧客対応は、税理士としての信頼性や専門性をアピールする効果があるでしょう。
また、駅近の立地にあることが多いため、顧客にとってアクセスしやすく、満足度の向上につながります。
受付サービスがあるバーチャルオフィスでは、来客の案内や取り次ぎもプロフェッショナルに対応してもらえるため、顧客に良い印象を与えることが可能です。
必要に応じて複数の会議室を同時に利用すると、異なる案件を並行して進めることもできます。業務効率の向上と顧客サービスの充実を同時に実現できるといえるでしょう。
税理士が開業時に事務所として登録できる場所

税理士が開業時に事務所として登録できる場所は、下記の3種類があります。
- 自宅
- 賃貸オフィス
- 物理的なレンタルオフィス
それぞれ詳しく解説します。
自宅を事務所として登録する
税理士は、自宅を事務所として登録し開業することが可能です。
自宅開業のメリットは、初期費用やランニングコストを大幅に抑えられる点や、通勤時間を省ける点が挙げられます。
実際に税理士登録をする際は、下記の書類が必要です。
- 建物の登記事項証明書
- 間取図
- 事務所設置同意書(自宅が賃貸・集合住宅などの場合に大家や管理組合から取得)
- 業務の拠点となる部屋の写真
同居家族の同意やプライバシーへの配慮、住所の公開(名刺やホームページへの記載)が必要となる点には注意が必要です。
賃貸物件の場合は、業務用途で使用することを禁止している大家さんもいるため許可を取る必要があります。
別途、小規模な賃貸オフィスを借りて事務所として登録する
税理士が小規模な賃貸オフィスを借りて事務所登録する場合、一定の条件を満たせば問題なく登録が可能です。賃貸オフィスの場合は、「税理士事務所の実体」として独立性・継続性が確保され、実際に業務可能な環境であることが求められます。
そのため、税理士登録時には「賃貸借契約書(写し)」や「事務所設置同意書(賃貸契約書に用途で“事務所”と明記されていれば不要)」、事務所の写真や間取図などの書類を提出します。
バーチャルオフィスや住所貸しサービスのように実体のないオフィスは認められませんが、小規模でも物理的に専有できるスペースであれば、社会的信用や顧客対応の観点からもメリットです。
契約前に、賃貸物件の用途制限や税理士会の登録要件を必ず確認しておくことが重要です。
実態のあるレンタルオフィスを事務所として登録する
税理士がレンタルオフィスを事務所として登録することは、必要条件を満たしていれば可能です。レンタルオフィスの中でも「完全個室型」や机・椅子・電話など必要な設備が備わり、本人が通常執務できる実体があるスペースなら、税理士会への事務所登録や法務局への開業届も認められています。
レンタルオフィスを事務所として登録する場合、賃貸契約書や室内写真の提出、実際の使用実態があることの証明が求められます。
レンタルオフィスは初期コストやランニングコストを抑えられ、備品やインフラが揃っているため、事業をスムーズに始められるのが大きなメリットです。都心や好立地にオフィスを持てること、受付や会議室などのサービスが利用できる点も魅力です。
一方、バーチャルオフィスや住所貸し、フリーアドレス型の共用スペースは「実体拠点」がないため、税理士事務所の登録には利用できません。契約前に「個室で登記利用が可能か」など、必ず要件を確認しましょう。
オフィスを借りる以外に税理士が利用できるスペースのメリット・デメリット

税理士業務において、事務所として登録せずにサテライトオフィスとして下記の設備を利用できます。
- レンタルオフィス (個室型)
- シェアオフィス(個室ブース型・固定席型)
- コワーキングスペース (固定席・時間貸し型)
それぞれの特徴を解説します。
レンタルオフィス (個室型)
個室型のレンタルオフィスは、税理士業務に必要な独立性と機密性を確保できる理想的な選択肢の一つです。
レンタルオフィスには、下記のメリットがあります。
- 完全な個室環境により顧客との面談時のプライバシーが完全に保護されること
- 24時間利用可能な場合が多く、柔軟な働き方ができること
- 受付サービスや会議室、コピー機などの共用設備が充実している
また、賃貸オフィスと比較して初期費用が抑えられ、契約期間も柔軟に設定できます。
一方。下記のデメリットがあります。
- 月額費用が通常の賃貸オフィスより高額になる場合があること
- 内装や設備の自由度が限られること
- ほかの利用者との共用部分があるため完全に独立した環境ではないこと
また、長期利用の場合は総コストが割高になる可能性があります。税理士会への登録においては、個室型であれば主たる事務所として登録可能な場合が多いですが、事前に運営会社との契約内容や使用条件を確認し、開業の条件に準拠している必要があります。
シェアオフィス(個室ブース型・固定席型)
シェアオフィスは、コストパフォーマンスと必要最小限の機能を両立させた選択肢です。
個室ブース型のメリットは、下記のとおりです。
- ある程度のプライバシーを確保しながらコストを抑えられること
- ほかの専門職との交流機会があること
- 立地の良い場所に多く存在すること
固定席型では、毎日同じ席を使用できるため、業務の継続性が保たれます。
デメリットは、下記のとおりです。
- 完全な個室ではないため顧客との重要な面談には不向きであること
- 騒音や他の利用者の影響を受けやすいこと
- 機密情報の取り扱いに制約があること
税理士会への登録においては、個室ブース型でも構造や使用条件によっては主たる事務所として認められない場合があります。事前に税理士会や運営会社に確認することが必要です。
利用を検討する際は、セキュリティ対策、利用時間の制限、会議室の利用可能性などを総合的に評価しましょう。
コワーキングスペース (固定席・時間貸し型)
コワーキングスペースは、コストを抑えて業務を行える選択肢ですが、税理士業務には制約が多いのが実情です。
固定席型のメリットは、下記のとおりです。
- 低コストで毎日同じ場所で作業できること
- さまざまな業種の人とのネットワーキングが可能なこと
- 立地や設備の充実度が高いこと
時間貸し型では、必要な時だけ利用でき、初期投資を最小限に抑えられるでしょう。
デメリットは、下記のとおりです。
- オープンスペースのため機密情報の取り扱いが困難であること
- 顧客との面談には適さないこと
- 電話対応が制限される
税理士会への登録においては、コワーキングスペースを主たる事務所として登録することは不可能と言えるでしょう。そのため、補助的な作業場所としての利用に留まることが多いです。
利用を検討する場合は、セキュリティポリシー、利用規約、他の利用者の業種などを確認し、税理士業務に支障がないかを慎重に判断する必要があります。
自宅兼事務所
自宅兼事務所は、開業初期の税理士にとって現実的な選択肢の一つです。
自宅兼事務所のメリットは、下記のとおりです。
- 賃料負担がなく固定費を最小限に抑えられること
- 通勤時間が不要で時間効率が良いこと
- 家族との時間を確保しやすいこと、
- 税務上の家事按分により経費として計上できる部分があること
また、事務所の環境を自由に整備でき、業務に最適化したレイアウトが可能です。
自宅兼事務所のデメリットは、下記のとおりです。
- 仕事と私生活の境界が曖昧になりやすいこと
- 来客対応が制限されること
- 近隣住民への配慮が必要なこと
- 家族への影響があることが挙げられます。
また、賃貸契約で事業使用が制限されている場合があります。税理士会への登録においては、自宅兼事務所として登録可能ですが、業務に必要な設備や環境が整っていることを証明する必要があります。
成功のポイントは、業務スペースの明確な区分、適切な設備投資、家族の理解と協力、近隣への配慮などです。
まとめ
税理士がバーチャルオフィスで開業することは、税理士法の規定により認められていません。バーチャルオフィスでは、下記の法的要件を満たせないためです。
- 物理的な業務スペースの確保
- 継続使用可能な場所の設置
- 人的・物的設備の整備
- 自らの管理下にある事務所の運営
しかし、バーチャルオフィスは営業活動の連絡先や一時的な来客対応の場として活用でき、コスト削減や都心部住所の利用、プライバシー保護などのメリットを享受できます。
開業時の選択肢としては、自宅兼事務所、小規模賃貸オフィス、個室型レンタルオフィスなどがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
税理士法の要件を満たしながら、自身の業務スタイルと予算に合わせてバーチャルオフィスを一時的な作業場所として使用することは可能です。
都心部で来客対応ができるメリットがあるため、本拠地としての事務所を確保しながら上手にバーチャルオフィスを活用しましょう。




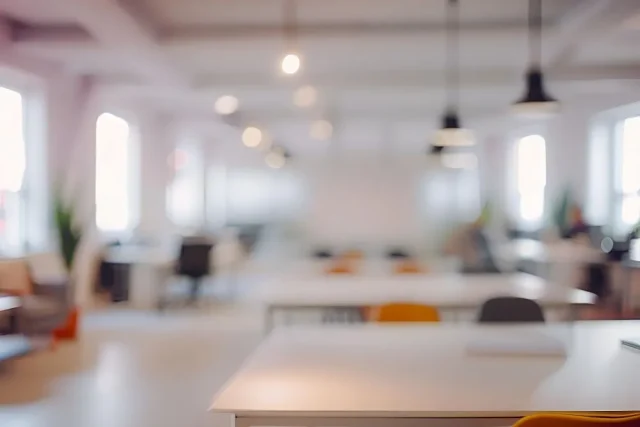
コメント